桑の実色(くわのみいろ)
熟しきった桑の実の色のような暗い赤紫色を言う。「桑染」とも呼ぶ。
藤鼠(ふじねずみ)
藤色を鼠がからせた柔らかい青み紫を言う。「新駒色」ともよばれた。
藤色(ふじいろ)
藤の花のような浅い青みの紫で、「若紫」とも呼ぶ。
二藍(ふたあい)
鈍い青紫色です。藍の上に紅花で染めて紫にする染めで、「二藍」は藍がふたつという意味。
染め方を呼び名に使うのは平安時代からある色名としては珍しいものです。二つの藍とは「紅」と「藍」をさします。紅色は呉の国からきた藍と言われており、「呉藍」という呼び名でも知られています。源氏物語の「空蝉」に、“白きうすもの単かさねで、二藍の小袿だつ物、ないがしろに着なして”という記述があります。
光源氏が遠い場所から二人の女を覗き見している場面で、二藍の衣を着る空蝉を識別できたと言うくだりの表現です。
当時から貴族のあいだでは定着していた色名であったことがうかがわれます。
紫苑色(しおんいろ)
やや青みをおびた薄紫色。「しおに」とも言います。紫苑の花の色のような、紫草からとれる染液で何回も繰り返して染められる紫色。
紫苑とはキク科の多年草で、秋に薄紫の素朴な花を咲かせます。旧暦の6月~9月頃まで用いられた秋の狩衣の色でもあります。
滅紫(めっし)
暗い灰紫色を言います。「けしむらさき」とも呼び、高温で染めることにより紫の色味に渋い鈍味を出した色です。
色を表現するのに「滅」という修飾語はよく使われますが、「くすんだ」「灰味のある」と言う意味合いがあります。「外出着の色」とされていたようです。
深紫(こきむらさき)
紫根、灰汁、酢を用いて染めた、濃い紫色を言う。衣服令の定めによると、臣下最高位の色で「禁色」としていた。「こき色」と呼ばれた。
薄色(うすいろ)
薄紫色。薄色といえば何色に限らず、淡い色をさしますが、色名上の「薄色」は淡い紫のことです。紫草の使用量は「深紫」の6分の1。
紫色が淡いので「聴色(ゆるしいろ)」とされていましたが、それなりの格式のある色でした。
半色(はしたいろ)
紫根染めで表された紫の中間色。「半」は中途半端の意。「延喜式」の染め方の規定による色位の紫からは外れてた半端な色ということで、禁色の制約からは外された色でした。といっても平安時代にはそれなりに社会に浸透した色名だったようです。深紫と浅紫の中間の、中紫より淡く、薄色より濃い色を言います。
中紫(なかのむらさき)
紫色は紫草の根を湯でぬらして揉みながらその表皮にある色素を出す。媒染剤は椿の灰を用いて発色させる。
竜胆色(りんどういろ)
秋の野草竜胆の花に見るような柔らかい感じの青紫を言う。
菫色(すみれいろ)
菫の花の色のような艶麗な、青みの冴えた紫を言う。
紫(むらさき)
「本紫」と呼ばれる色です。紫根(しこん)と灰汁と酢による低温染の濃艶な紫色をいいます。紫根とは紫草の根でムラサキ科の多年草、シコニンという色素が染料となります。
紫草は日本には古くから存在する植物で、紫の花が群れて咲きます。現代ではほとんど野生の姿は見かけなくなりましたが、その昔は「武蔵野の紫草」といわれるほど、関東一帯に咲き乱れていたとのこと。平安時代の頃は主に関東、下総、常陸、下野の国からこの紫草を調達していたようです。染めるのに手間ひまと技術を要したためか、身分の高い貴族しか着用が許されませんでした。貴族社会では最高権威の象徴であるとともに、一方では優美な気品のある情緒豊かな色でもありました。
竜胆色(りんどういろ)
秋の紫をモチーフにした、数少ない色名。
菖蒲色(あやめいろ)
花菖蒲の花の色に見る冴えた赤みの紫色を言う。
紅藤(べにふじ)
紅がかった藤色、即ち、赤みの淡い紫を言う。
江戸紫(えどむらさき)
日本では貴族社会の頃より、紫草は各地で自生又は栽培されていましたが、武蔵野産がもっとも有名でした。しかし江戸時代に入ると、当時まだ新興都市であった江戸には上方に対抗できるほどの工芸技術や名物はなく、ゆういつ紫草を使った染のみが勝れるとも劣らぬものであったため、江戸紫と名づけ江戸の特色をアピールと思われます。京紫より青みが強く歌舞伎の色としても用いられるなどして、粋な色とされました。杜若の花の色に似た、濃艶な赤みの紫を言います。「杜若」とも同色系の色です。
京紫(きょうむらさき)
伝統の染めの技法を受け継いだ赤みのある紫。京の都には昔から受け継がれてきた紫染めの秘伝があります。それが京紫です。江戸紫に対する色名として江戸時代についた名だと思われます。華やかでな優美さを好む貴族社会では紫は常に羨望の的でしたが、江戸時代になると、「今世は京紫を賞せず、江戸紫を賞す」と書かれるなどし次第に時代の変遷の中に埋もれていきました。
古代紫(こだいむらさき)
紫根の根を材料として染める紫は今日の合成染料による彩度の高い紫を望むべきも無かった。
昔の鈍い色を「古代紫」と言った。
紫根色(しこんいろ)
紫草の根に含まれている色素はそのままでは赤みを呈している。これで染めて乾燥させた赤みを帯びた深い紫を言う。
葡萄鼠(ぶどうねずみ)
古代の「蒲萄」の色を鼠かからせた、鈍い赤紫を言う。
蒲萄色(えびぞめいろ)
山葡萄の実が赤紫に熟した色。紫根と灰汁と酢で染めた赤みの紫色を言う。天武天皇の色制では、深・浅の二級に分けられている。
淡蒲萄(うすえび)
「延喜縫殿式」の用法よると「蒲萄」は表示色のようになる。「淡蒲萄」は薄い方の「蒲萄」を言う。
似せ紫(にせむらさき)
暗い赤紫色。高価な紫根の代わりに、蘇芳或いは茜を用いて染めた紫の代用染です。色味としては、江戸紫と京紫の中間色の色合い。紫根を用いる「本紫」に対するもので、本物に比べると品位は落ちるとされましたが、それでも庶民にとって、紫は憧れのまとでした。茶屋女でも紫の着物をきてみたい。井原西鶴は、伊勢参りの客の手引きをする、似せ紫に派手な赤襟をつけた茶屋娘を描いています。

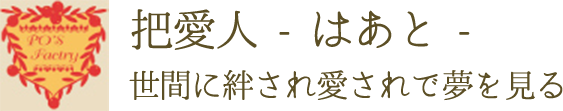




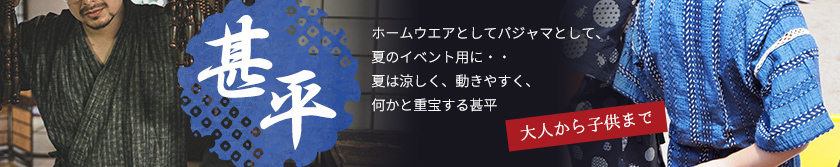

 和雑貨
和雑貨 伝統工芸品
伝統工芸品 着物ギャラリー
着物ギャラリー 店長日記
店長日記





