黄蘗色(きはだいろ)
抜けるような鮮やかな発色の黄色です。日本古来の染料で、奈良時代の写経の紙にも黄蘗染めのものがあり、防虫のために染めたものと思われます。
黄蘗はミカン科の落葉樹の高木で、深山に自生する植物です。その樹の内皮の黄色のあまりの鮮やかさから、染料として用いられたとされますが、以外に単染めではなく、下染めとされることが多いようです。黄蘗の内皮の煎じ汁と灰汁で染めます。
黄丹色(おうたんいろ)
冴えた赤橙色。古代朝廷の時代より皇太子の礼服として制定されていた。曙の太陽の色を模して、支子の下染めに紅花を上掛けして染めました。
天皇が神事に用いた白につぎ、紫の上に位置する禁色の位の高い色でした。
栗梅色(くりうめいろ)
栗色がかった濃い赤茶色を言います。マロン色に近い色合いで、茶系の中でも明るい色合いです。栗色と言うと日本では一般的にコーヒーブラウンのようなコクのある茶系の色をさしますが、その茶に秋の紅葉の赤を吸わせた様な秋の中間色。栗梅に類する色に「栗皮茶」がありますが、これは「栗梅」より黄味が強い茶色です。
控えめな色として、紬や小紋などに配色されますが、金糸の刺繍、箔使いなど彩をそえれば、たちまち上品な華やかさが増し、帯や色留袖の色にとしても使われます。
山吹色(やまぶきいろ)
花にちなんだ黄色系の色名としては比較的古く、平安時代から親しまれている色です。山吹の花の色のような、冴えた赤みの黄色で女郎花色よりも赤みがかっており、「マリーゴールド」、「黄金色」にも近い色です。「山吹」はバラ科の落葉低木で、小ぶりで可憐な花を咲かせます。
イギリスではジャパン・ローズとも呼ばれ、日本の花と言う印象が強くもたれているようです。もともと野山に自生する植物ですが、その花の愛らしさからか、観賞用に軒先に埋め込む人が今も多いようです。
黄櫨染(こうろせん)
蘇芳系の赤みを含んだ黄褐色。櫨の木の若芽の芯の部分の「黄」の下染めに、蘇芳又は紫根を上掛けしてだした色。太陽の色を象徴した色で、日の光によって赤褐色にも見えます。弘仁11年(820年)に天皇の礼装の色とされ、天皇以外は、用いることの出来ない「絶対禁色」とされました
大変微妙な染色なので、暦代天皇の御衣でも、同じ色に見えることはほとんどないということです。
黄朽葉(きくちば)
「朽葉色」から分化した色の一つで、黄ばんだ銀杏の葉の色のような黄褐色、山吹色に茶をかけたような色あいです。「源氏物語」にも「朽葉のうすもの」との記述があります。「朽葉」とはかなさと、もののあわれを感じさせる韻を踏んでいるようです。洋名では、オールドゴールドに近い色。
落ち着きの中に明るさがある色です。この色をぐっと濃くすると、黄枯茶という言葉になり、テラコッタのような濃い色合いになります。刈安をベースに染められたようです。
櫨染(はじぞめ)
山櫨の黄色い心材の煎汁と灰汁で染めた深い暖味の黄色を言う。
女郎花(おみなえし)
山野に自生する多年草の女郎花の花の色を模した“緑味の冴えた黄色”を言います。女郎花は多年草で、秋の七草のひとつです。
刈安色(かりやすいろ)
やや緑にくすんだ黄色です。山野に自生する草、イネ科の多年草でススキに似ている植物です。刈り安いことからこの名がついたようです。
日本でも古代から存在する伝統的植物染料のひとつで、10世紀の「延喜式」でも重要な染料として記されています。刈安の草を細かく刻んで作った煎じ汁に、椿の灰汁やミョウバンで染めます刈安は他の染料と掛け合わせて使うことも多くあります。
菜の花色(なのはないろ)
あぶら菜の花色のような、明るくクールな黄色を言います。歌に詠われるような一面の黄色い菜の花畑が日本の風景として定着したのは、油菜から出来た灯油を大量に消費するようになってからの、ごく近世のことです。菜種油色という言葉のほうが歴史的には、古くからあるようです。菜種油色はオリーブ色に近い色で別色です。
楊梅色(あせんいろ)
亜熱帯性の植物で日本や中国に生育している。木の皮に色素があり、これが明礬、又は椿の灰で黄色に発色する。
玉子色(たまごいろ)
古代から中世にかけては、卵の殻から想像される鳥の子色のような黄白色が定着していたようですが、近世では卵の中身の色に意識がむけられ、卵色と言うと中の卵黄部分をさし、玉子色=やや赤みがかった明るい黄色と言うイメージになってきました。卵が日常の食卓に上る事が一般化してきたことを示していると思います。江戸時代にはいると鳥の子色は気取りすぎた言葉として、一般庶民の間では使われかったようです。

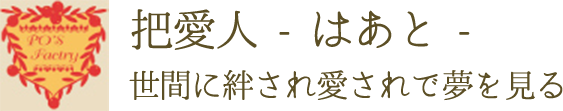




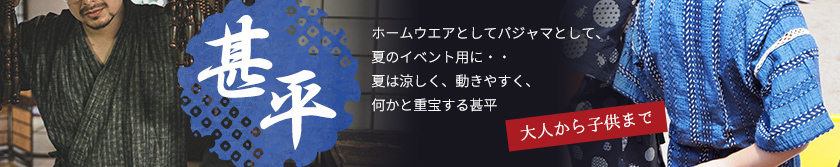

 和雑貨
和雑貨 伝統工芸品
伝統工芸品 着物ギャラリー
着物ギャラリー 店長日記
店長日記





